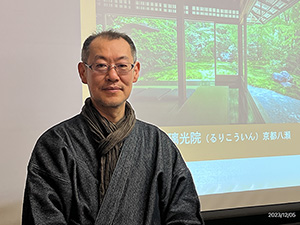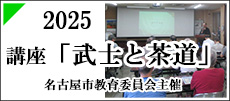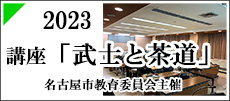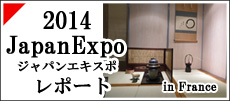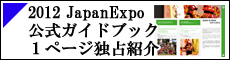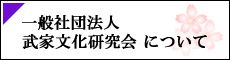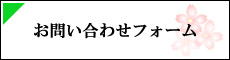|
|
||
|
|
 |
 |
|
|
||
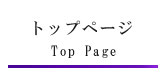 |
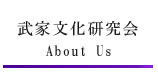 |
 |
 |
 |
 |
「<なごや学>古のなごや 武士のイロハ」
|
2025年9月18日、名古屋市教育委員会が主催する5回講座「<なごや学>古のなごや 武士のイロハ」において、「武士と茶道」の講座の講師を、当会代表の中島が務めさせていただきました。 この講座は、「武士の暮らし」「武士と刀剣」「武士と家紋」「武士と茶道」「武士と住まい」の全5回で構成されており、各回の講師は大学の先生方が担当されました。定員30名のところに100名を超える応募があり、大変人気のある講座でした。
講座では、茶道未経験で武家文化に興味をお持ちの参加者の皆さまに向けて、私自身が抱いていた疑問を起点に、茶の湯の誕生から戦国武将が茶の湯を取り入れた理由、江戸の平和な時代における茶の湯、明治期の大変革、そして現代茶道へと続く流れをお話しさせていただきました。 受講者の皆さまは武士に強い関心をお持ちでしたので、信長軍団に多く残る茶の湯にまつわる逸話――「御茶湯御政道」や、滝川一益、松永久秀、佐久間親子、豊臣秀吉、徳川家康、黒田官兵衛、石田三成、大谷吉継などの有名武将に関するエピソードを交えながらお話ししました。 また、利休のもう一つの顔である「堺の商人」と戦国武将との関わりについても触れ、堺商人が「鉄砲」という当時のゲームチェンジャーを一手に握っていたことから、彼らが“キングメーカー”たり得たのではないか、という仮説もご紹介しました。 さらに、「本能寺の変」を茶の湯の視点から捉えてみると、新たな解釈や思惑が浮かび上がってきます。あくまで推測の域は出ませんが、参加者の皆さまと一緒にそうした仮説を考えていくことは、歴史の醍醐味の一つだと感じました。 2時間にわたる講義と質疑応答の後には、数名の方がご挨拶に来てくださり、「疑問が晴れてスッキリしました」「講座がとても面白かった」「本能寺の変の話がとても興味深かった」といった感想をいただきました。後日行われた参加者アンケートでも、「非常に内容が濃く、とても面白かった」新しい視点の考察が新鮮だった」といったご意見を頂戴しました。 茶道に触れたことはないが、歴史、特に戦国期に興味をお持ちの方は多くいらっしゃいます。本講座のように、戦国武将と茶道の関わりを知っていただくことで、少しでも茶道に関心を持ち、体験していただくきっかけになればと思っております。
※武家茶道等の講義・公演のご依頼は、お気軽にお問い合わせください |
| ■サイトマップ | |||
|
■武家文化研究会 ■イベント派遣 ■文化財を守る |
■欧州コーディネイト ■日本の伝統を紹介 ■武家文化技能士・活動団体紹介 |
■活動報告 ■その他 |